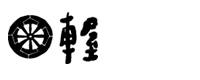車屋の歴史
豊かな精神性と雰囲気が脈々と受け継がれた場所
 車屋の歴史は、先代伊藤鐘治郎(一九八九年六月没)が、昭和五年新宿に『ウォーグ』『ミロ』そして、紀伊国屋書店の中に、武蔵野茶廊という喫茶店を開いたことから始まります。
当時、武蔵野茶廊は文明開化の微勲を持っており、そこに出入りする事は、あたかも西洋文化の匂いにふれた様な思いを持つ事が出来たものと思われます。
中でも富田常雄、田村泰次郎が、武蔵野茶廊を書斎がわりとして利用し構想を練り、姿三四郎、肉体の門の一部を執筆した事が特筆されます。 その後、酒場『キュピドン』『どれすでん』と、まるで欧州のカフェを思わせる様なユニークな店舗を新宿に開店していきました。
これらの店では、日本の文化芸術界を代表する様な人達(下記参照)が、活発な芸術論や人生論を戦わせる場で、その豊かな精神性と雰囲気が脈々と受け継がれ、今日の車屋となっています。若き日の芸術家や文化人が、口角泡を飛ばして夢や、恋や、芸術や、人生を語った事が、ほうふつされます。
その間、戦争にあったり、幾多の遍歴を経て、昭和三八年新宿コマ劇場の横に現在の車屋本店を出店し、連日行列が出来る様な喝采を受け、平成三十年に本店を『隠れ里車屋』(神奈川県藤沢市)に移すまで、私共車屋は創業時の和洋混在の時代から厚底茶髪、草食系男子、肉食系女子迄、新宿の移り変わりを、九十予年に渡って静かに見守って来た店と云えるのではないでしょうか。
車屋の歴史は、先代伊藤鐘治郎(一九八九年六月没)が、昭和五年新宿に『ウォーグ』『ミロ』そして、紀伊国屋書店の中に、武蔵野茶廊という喫茶店を開いたことから始まります。
当時、武蔵野茶廊は文明開化の微勲を持っており、そこに出入りする事は、あたかも西洋文化の匂いにふれた様な思いを持つ事が出来たものと思われます。
中でも富田常雄、田村泰次郎が、武蔵野茶廊を書斎がわりとして利用し構想を練り、姿三四郎、肉体の門の一部を執筆した事が特筆されます。 その後、酒場『キュピドン』『どれすでん』と、まるで欧州のカフェを思わせる様なユニークな店舗を新宿に開店していきました。
これらの店では、日本の文化芸術界を代表する様な人達(下記参照)が、活発な芸術論や人生論を戦わせる場で、その豊かな精神性と雰囲気が脈々と受け継がれ、今日の車屋となっています。若き日の芸術家や文化人が、口角泡を飛ばして夢や、恋や、芸術や、人生を語った事が、ほうふつされます。
その間、戦争にあったり、幾多の遍歴を経て、昭和三八年新宿コマ劇場の横に現在の車屋本店を出店し、連日行列が出来る様な喝采を受け、平成三十年に本店を『隠れ里車屋』(神奈川県藤沢市)に移すまで、私共車屋は創業時の和洋混在の時代から厚底茶髪、草食系男子、肉食系女子迄、新宿の移り変わりを、九十予年に渡って静かに見守って来た店と云えるのではないでしょうか。
昭和6年創業の「武蔵野茶廊」
多くの芸術化や文人が訪れ、ここから多くの文学作品が世に送り出されていきました。
新宿駅周辺で最も歴史のある喫茶店として、多くの方々に愛されておりました。

昭和15年当時の「武蔵野茶廊」店内 この店内で作家・富田常雄が「姿三四郎」の原稿を書き、田村泰次郎は「肉体の門」を執筆するなど、作家達の書斎がわりに利用されていました。所蔵:国立国会図書館

閉店前の「武蔵野茶廊」店内 昭和6年(1931)二幸裏の新宿喫茶街に開店、落ち着いた雰囲気の店で、若手の芸術化や文化人が数多く訪れました。 戦災で建物は替わりながらも、営業を続けておりました。

武蔵野茶廊跡地の御案内
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-21-2
絵 : 堀 潔
旬の食材

牡蠣(かき)
日本では縄文時代の貝塚から見つかっており、ヨーロッパではローマ帝国時代から食され、その長い歴史の中で、身だけではなく殻にも効能が認められ、昔から世界各地で滋養強壮食として使用され「海のミルク」とも呼ばれてきました。グリコーゲンの含有量が増える秋から冬が旬と言われ、産卵期に入る5月~8月頃は味が落ちる上中毒を起こしやすいので、「Rが付かない月には食べるな」「桜が散ったら食べるな」などといわれています。
英名 : Oysters
ずわい蟹(かに)
深海に生息する大型の蟹。「ずわい」とは、細い木の枝を意味する古語{楚(すわえ、すはえ)が訛ったとされ、漢字で「津和井蟹」とも書かれる。体色は暗赤色で、熱を加えると赤くなる。塩茹でや蒸し、鍋で食され、新鮮なものは刺身や寿司種としても利用される。上品で甘みがある肉だけではなく、中腸線(蟹味噌)、卵巣も食されます。 一部の漁港でずわい蟹をブレンド化し、「越前ガニ」、「松葉蟹」などと呼ばれていますが、異なる蟹ではなく同じずわい蟹です。
英名 : Tanner Crab
河豚(ふぐ)
中国で食用されるフグが淡水域に生息していた為、又泣き声が豚と似ている事から漢字では「河豚」と表記されます。大変毒性の強い河豚ですが、2000年以上前の中国、日本での食用が確認されています。秀吉の「ふぐ食禁止令」、徳川幕府の「当主が河豚で死んだら家名断絶」、明治政府の拘置・科料に処す法令、等 「河豚は食いたし命は惜しい」多くの食通をうならす美味と言うことです。河豚取扱い資格は都道府県ごとに定められ、有毒部位の管理には鍵つきの容器を用意し、適切な廃棄が義務付けられています。
英名 : Puffer Fish / Globefish / Fugu